Blog
- 【ヴァンガードスミス10周年記念企画②進化】「“被害者をつくらない”――近隣トラブル対応から進化した〈防犯対応実践訓練プログラム〉とは?」

店舗スタッフを“守る”ために、企業が果たすべき防犯対応とは――。
非対面接客の普及により、顧客対応の場がオンラインへと移行する一方で、強い怒りや不満を抱える一部の顧客が「確実に人がいる場所=店舗」へと向かう傾向が容易に想像できるようになってきました。こうした時代背景の中、株式会社ヴァンガードスミスが2025年6月に開始した〈防犯対応実践訓練プログラム〉は、これまで提供してきた「近隣トラブル解決支援サービス」で培った知見を基盤に、“被害者をつくらない”という理念のもと開発された、実践型の防犯研修サービスです。
ヴァンガードスミスの10周年記念企画・第2回では、このサービスの設計思想や誕生の背景、そして「事件にさせない力」の進化について、代表の田中慶太にインタビューしました。
「被害者をつくらない」――トラブル対応から“実践型防犯”への進化
近隣トラブル解決支援という“事件未満”の現場で長年培ってきた経験が、いま“現場防犯力”として進化を遂げています。万が一襲撃された場合に適切な対処で現場生存率を上げる―それがこれまで蓄積されたノウハウを元に、「被害者をつくらない」ための研修を構築した考え方の核心です。
逆恨みからの襲撃や加害を目的とした暴力行為など、金銭目的とは異なる新たな脅威にどう備えるか。その答えが、本プログラムに込められています。
ーまずは「防犯対応実践訓練プログラム」の概要を教えてください。
不特定多数の来店者がある店舗を対象に、カスタマーハラスメントや襲撃行為などに備えた実践的な防犯対応を学ぶプログラムです。主な内容として、以下が挙げられます。
- 望まない面談要求や過剰なクレーム対応の具体的な対処法
- 実際に襲撃が発生した場合や、不審者への対応方法
- 防犯資材(さすまた、盾、ネットランチャーなど)の設置・使用方法
上記を通して、有事に備えるということを皆様に体験していただくことが目的です。

ーこのサービス立ち上げのきっかけ、また特にどのような業種・業態の現場に危機感を感じたのか教えてください。
不動産業やコンビニ、携帯電話販売店など、不特定多数の来店者を受け入れる業態において、実際に怪我を伴う事件が発生しており、こうした現場のリスクを目の当たりにしたことがきっかけです。
例えば、従来コンビニでは、現金を取り扱うことから強盗に襲われることがありました。しかし、現在はキャッシュレス決済の浸透により、現金の取り扱いが減少傾向にあります。このような背景から、強盗目的に限らず店舗を襲撃するといった事件も起きており、「私たちの顧客も一定のリスクの中で事業を行っているのではないか」という危機意識を抱きました。ひとりでも被害者を減らしたいという想いから、防犯訓練研修サービスの立ち上げに至っています。
ーAIやチャットボットなどの普及と、防犯の関係についてどのように見ていますか?
近年、電話が自動的に転送されるIVRや、お客様からの問い合わせをAIが対応するチャットアプリなどの普及により、人を介さずに対応する仕組みと環境に変わってきています。「直接話を聞いてもらえない」ことへの不満が高まったことが、望まない面談要求(カスタマー・ハラスメント)などの増加につながっていると考えています。対面でのトラブル発生リスクの高まりから、防犯対策の重要性がより増してくるだろう、と捉えています。
ーこれまで手がけてきた近隣トラブル解決支援やカスハラ対策サービスが、どのように本サービスのベースになっていますか?またそこからどのように「進化」したと捉えていますか?
主に深刻なカスタマーハラスメントへの対応支援が本サービスの原点です。そこに加え、業界背景的に店舗襲撃といった特有のリスクが実際に起きているという事実を踏まえ、防犯対応まで含めた、より実践的かつ危機対応型のサービスへと進化させました。
“現場で使える”防犯力とは――体感型プログラムの真価
いざというときに体が動かなければ意味がありません。同プログラムでは、研修を通じて従業員が「いざ」という場面で即応できる力=“体感型の防犯力”を習得することを重視しています。
防犯管理士が現地で指導し、通報・避難といった一連の動作をシミュレーション形式で訓練することで、頭だけでなく身体でも「適切な対応」を体得できる設計です。
ーサービスの研修内容・進行はどのような構成になっていますか?また、「体感型研修」として設計する上で、特に重視したポイントについて教えてください。
研修は、大きく分けて「座学」と「実地訓練」の2つの構成で実施しています。
座学では、元警察官のメンバーが犯罪に関する知識や、不審者の判断基準について具体的な事例を交えて解説します。また、110番通報後の「警察到着までの空白の時間」にできる対応行動の選択肢についても学びます。
実地訓練では、不審者への声かけや機材の使い方、防犯機材を実際に使用する場合の体の動かし方など、各タイミングを踏まえて実践します。これは「いざというときに体が反応する」ことを目的とした体感重視の設計です。
研修を行うのは、当社で「防犯管理士」として認定された当社メンバーです。当社では、規定の研修を修了した者に「防犯管理士」として独自の認定を行っています。彼らが現地で指導し、通報・避難といった一連の動作をシミュレーション形式で訓練しています。
また、各店舗の形状に応じた避難経路の確保や、防犯機材の設置方法を個別に判断・提案することも可能です。これらは標準プログラムの一環として実施しており、講習だけでなく、防犯コンサルティングの要素も含まれています。

ー元警察官の視点が、研修にどのように活かされていますか?
元警察官は、交番襲撃に備えた訓練や、不審者・興奮した者への対応にも慣れています。彼らによる実体験や具体的な実例をもとに、不審者対応について解説することで、受講者がイメージしやすく、より実践的な内容になっています。なお、防犯管理士は現時点ですべて元警察官のメンバーが認定されています。
また一般的には、110番通報後、すぐに警察が到着すると思いがちですよね。しかし、警察が到着するまでには平均8分24秒の時間があり、その間に全てのコトが終わってしまう傾向にあります。元警察官としてその現場を経験し知っているからこそ、残念ながら何かトラブルが発生したときには、初期対応は自分たちで行う必要があるという事実を理解いただき、「その時間に何ができるか」を知ることが非常に重要だとお伝えしています。
「人を守る経営」の時代に――企業の信頼と“防犯力”の関係
近隣トラブルの解決支援から、“人的資本を守る防犯研修”への進化は、当社の社会的責任の広がりを象徴しています。
従業員を守る力は、企業の信頼を守る力でもある。このプログラムは、防犯対応のノウハウを誰もが活用できる“インフラ”として社会に還元する取り組みでもあります。
ー防犯対応を「人的資本経営」の観点から捉える理由について教えてください。
防犯対応は、「会社が社員を守る」という強いメッセージとなり、人的資本への重要な投資と位置づけられます。実際、多くの経営者の方がその必要性を感じながらも、具体的な対策に踏み出せずにいるという声を多く聞きます。しかし、「社員を守る責任がある」という認識は共通しており、防犯対応実践訓練プログラムの提案に対して否定的な反応はありません。
現在の日本社会では、深刻な人材不足が続いています。その中で、企業が「人材をいかに大切にするか」という視点を持つことは、これからの企業経営において欠かせません。このような観点から、防犯対応実践訓練プログラムは非常に重要だと考えられます。
ーこの研修が企業・社会全体にどんな価値をもたらすと考えていますか?
この研修を通じて、まず企業内に防犯意識が広がり、その意識を持った社員が増えることが大きな価値です。防犯意識が高い社員が揃う店舗は、犯罪の標的になりにくくなると考えています。また、万が一トラブルが発生しても、最初の行動が変わることで被害を最小限に抑えることができるはずです。こうした効果を実現するためにも、私たちは実際の事例をもとにした実践的な訓練を提供しています。
ー今後、どのような形でプログラムを進化させていく予定ですか?
当社のサービスを取り扱っていただいているお客様の中で、不特定多数の来店客がある業態の企業には定期的な訓練の実施を広げていきたいと考えています。それによって、いざというときに冷静に対応できる人材をひとりでも多く育成し、世の中全体の防犯力の向上に貢献できるよう、取り組んでまいります。

次回予告 ――「“言葉の暴力”が争いを生む前に」誹謗中傷をしない・させない社会を目指して
第3回では、誹謗中傷や感情の暴走を“未然に防ぐ力”を育てる取り組みに注目します。
近年、インターネットだけでなく近隣トラブルの火種にもなりつつある“言葉の暴力”と”ミスコミュニケーション”。ヴァンガードスミスは、各地で開催する子ども向け防犯イベントなどを通じて、「思いやり」や「相互理解」、「冷静さ」の大切さを伝える啓発活動を続けています。
未来を担う世代にこそ届けたい、“争いを生まない力”とは?
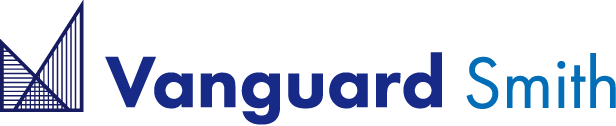
 前の記事へ
前の記事へ