Blog
- 【ヴァンガードスミス10周年記念企画③啓蒙】「“言葉の暴力”が争いを生む前に――誹謗中傷をしない・させない社会を目指して」

SNSや匿名掲示板が普及し、誰もが気軽に言葉を発信できる時代になりました。便利さと自由度が高まる一方で、軽率な一言が他者を深く傷つけ、誹謗中傷や対立を引き起こすことも少なくありません。これらは目に見えない“言葉の暴力”として、時に人生や人間関係を大きく揺るがす力を持っています。
ヴァンガードスミスは、安全な暮らしを守る防犯の取り組みを通じて積み上げてきた知見を活かし、こうした言葉による暴力も社会課題の一つとして捉えています。「誹謗中傷をしない・させない社会」を目指し、未然に防ぐための啓発活動を展開することで、特に将来を担う子どもたちに対して、言葉の使い方やコミュニケーションの大切さを伝える取り組みにも力を入れています。
10周年記念企画の3回目となる本記事では、その活動の具体的な内容や背景にある想い、そして社会的な意義についてご紹介します。
▶本記事のインタビュー動画はこちら
現場で見てきた、“感情の暴走”がもたらすトラブル
ーこれまで10年、近隣トラブルの解決に向き合ってきましたが、そこで改めて感じる「問題の根幹」は何なのでしょうか?
近隣トラブルの根本には“感情”があります。相手を嫌いだと思う気持ちや処罰したい思い、自分は被害者だという感情などが積み重なり、高ぶっていくことで衝突や攻撃的な行動につながります。私たちはこうした構造を「感情の種類」と「その段階」で捉え、双方の感情を整理して日常生活に戻れる状態へ導くことを大切にしています。
典型的な事例が「子どもの足音」です。最初は「仕方ない」と思えても、音の大きさや時間帯、頻度が重なると「配慮がない」「非常識だ」という怒りに変わり、感情はエスカレートします。音自体が変わらなくても、長く続くことで不満は膨らみ、やがて天井を突いたり怒鳴り込んだりと行動に発展してしまうのです。
これを防ぐには、感情が高ぶる前に状況を確認し、冷静さを取り戻すことが必要です。相談員が双方の話を寄り添いながら聞き、事実を整理すると「実はここまで配慮していた」と見えてくる点があります。その事実を伝えることで「これなら受け入れられるかも」という歩み寄りが生まれます。
直接やり取りをすると感情がぶつかり合い、大きな衝突を招くリスクが生じる。だからこそ、第三者である相談員が対応することが重要であり、それが感情のステップを下げ、トラブルを解決へと導く要となるのです。

ーそれらの経験から、どんなことを強く感じるようになりましたか?
多くの近隣トラブルは、生活音や仕草が「嫌がらせでは」と誤解され、感情が高ぶることで起きています。だからこそ大切なのは、トラブルになる前に原因を確かめ、誤解を早期に解くこと。その役割を担うのが私たちの相談窓口です。
早い段階で相談いただければ、大きな争いを未然に防ぐ仕組みとして機能します。これまで現場で感情を鎮める取り組みを続けてきましたが、「そもそも起きないようにするには?」という問いが生まれ、それが現在の啓発活動の原点になっています。
「思いやり」や「冷静さ」も、防犯になる
ー世間的には“防犯”というと、警報や防犯カメラなどのツールを思い浮かべがちですが、ヴァンガードスミスでは「防犯」という言葉をどのように捉えていますか?
私たちは「人の心の持ち方」も防犯になると考えています。近隣トラブルの多くは感情が出発点です。だからこそ、まずは冷静さを取り戻し、相手の状況を想像し理解することが重要です。
双方が「相手にも事情がある」と思いやりを持ち、誤解を早く解消できれば感情は高ぶらず、争いを未然に防ぐことができます。私たちの配慮や理解を促すプロセスそのものが“防犯システム”になっているのです。
「感情に流されず、冷静に距離をとること」「相手を思いやること」――その二つの力を育むことこそが、争いの芽を摘む本質的な防犯なのだと思います。
実はこの考え方は柔道の《自他共栄》の精神に通ずるものがあり、防犯に非常に有効だと考えています。
ーこれまでヴァンガードスミスは、全国各地で、主に小学生を対象にした「防犯・柔道交流プロジェクト」を実施してきました。活動について教えてください。
「防犯・柔道交流プロジェクト」を始めたのは、私自身が柔道を通して得られた学びを子どもたちにも体験してほしいと思ったことがきっかけです。柔道のコミュニティは全国に広がっており、私も北海道から関東に出てきたとき、柔道着ひとつで新しい仲間と出会い、孤立せずに済んだ経験があります。さらに世界を見渡すと、日本人から柔道を学びたいと願う人々が数多く存在します。柔道は単なる武道ではなく、人と人をつなぎ、人生を支える大きな力になる――その実感を子どもたちに伝えたいと強く思いました。
これまで北九州、札幌、船橋などで、児童養護施設や地域の学校の子どもたち、少年柔道家たちと交流を重ねてきました。イベント前半の防犯教室では、体を動かしながら防犯について学ぶ実践プログラムを行います。困っている人を見かけたらどうするか、悪いことに巻き込まれそうな人をどう助けるか、自分の言葉が相手にどう伝わるか――子どもたち自身で考え、動いてもらう、より自分事化するやり方で進行しています。
この取り組みを通じて印象的なのは、子どもたちが真剣に、そして楽しそうに参加してくれることです。座学ではなく体を動かすからこそ記憶に残りやすく、いざというとき自然に行動につなげられる。柔道経験の有無にかかわらず、誰もが持つ“正義感”に火がつき、「自分ならこうする」と積極的に意見を交わす姿はとても力強さを感じます。

私は、この活動が将来の近隣トラブルを減らし、安心できる社会を築く基盤になると信じています。「誹謗中傷をしない・させない社会」を、次の世代からつくっていく。そのためにこそ、子どもたちに“思いやりの大切さ”を伝え続けたいのです。
柔道家・井上康生さんと届ける、“本当の強さとは?”というメッセージ
ー「防犯・柔道交流プロジェクト」には、当社取締役であり、柔道家の井上康生さんにもご協力いただいています。
私はもともと康生さんの大ファンで、柔道を通じて得られる魅力を子どもたちに伝えたいと考えていました。柔道普及を使命とする康生さんの想いと、防犯を広げたいという私たちの想いが重なり、このプロジェクトが誕生しました。
康生さんは子どもたちとの交流そのものを心から楽しんでいるように見えます。その楽しむ姿に子どもたちも自然と引き込まれ、「柔道って楽しい」と感じながら学んでくれています。技術面での解説やレクチャーももちろんありますが、それ以上に「助け合い、励まし合い、高め合う」という柔道の本質を伝えてくださっていると思っています。
実際、子どもたちは康生さんの指導で目に見えて技のクオリティが上がり、握手をしてもらった子が「もう手を洗わない!」「握手してもらったから柔道強くなれるかなあ!」と口々に話すなど、興奮と喜びに満ちた姿を見せてくれています。
「強いってどういうことか?」「本当に強い人って、どんなふうに人と接するか?」――その答えを、子どもたちは康生さんの立ち居振舞いから感じ取っているのだと思います。技術の指導にとどまらず、姿勢や言葉を通じて「自分を律すること」や「他人を思いやること」の大切さが自然に伝わり、子どもたちの心に深く刻まれていると感じます。

ー今後、このイベントはどのように展開していきたいと考えていますか?
今後は柔道家の仲間を増やし、講師陣を充実させて開催頻度を高めていきたいと考えています。
大規模なイベントよりも、地域ごとに地道に回を重ねることが大切だと思っています。その積み重ねが防犯の考え方を広め、柔道への理解を深める基盤になります。柔道コミュニティと連携し、地域に根ざした継続的な活動を目指していきます。

▶本記事のインタビュー動画はこちら
次回予告「“人を助ける柔道”から生まれた発想―全国の道場を、防犯の拠点に」
井上康生さんと共に取り組むプロジェクトをはじめ、私たちはこれからも「心の防犯教育」を広げていきたいと考えています。既に全国の柔道場を“地域防犯の拠点”として活用していくプロジェクトが進行中です。
柔道が大切にしてきた《自他共栄》の精神と、私たちの防犯事業が持つ親和性。その可能性について、次回の記事でさらに詳しくお伝えしていきます。
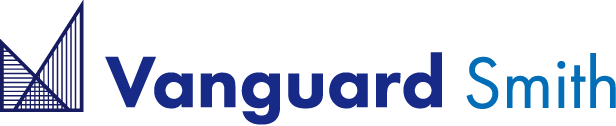
 前の記事へ
前の記事へ