Blog
- 【ヴァンガードスミス10周年記念企画①理念 】「“困っている人を助ける”ために――唯一無二の事業として確立した〈近隣トラブル解決支援〉の現在地」

株式会社ヴァンガードスミスは、2025年10月で創業10周年を迎えます。これまで、誰にも相談できずに苦しむ人が多い“近隣トラブル”という社会課題に、唯一無二の民間支援サービスとして向き合ってきました。
なぜこの事業が必要とされ、どのように発展してきたのでしょうか。10周年記念企画の連載初回となる今回は、創業者で代表取締役を務める田中慶太氏に、これまでの歩みについて聞きました。
▶本記事のインタビュー動画はこちら
“見えにくい社会課題”に挑み続けた10年――起業の原点と社会的意義
行政サービスや警察の枠では対応しきれない“グレーゾーン”―それを埋める存在として立ち上げたのが〈近隣トラブル解決支援〉事業だった。10年間の挑戦の背景には、「困っている人を助けたい」というシンプルだが強い信念がある。
―起業のきっかけ、また最初に「近隣トラブル解決」に着目された理由を教えてください
起業当初は“近隣トラブル解決”に限定しておらず、私が着目したのは、まだ“事件”になっていない、けれど困っている人がいるという「事件未満」の状態でした。
警察官時代、まだ被害は起きていないものの恐怖や不安を抱えて相談に来られる方はたくさんいました。しかし、まだ実際に被害が発生していない状況であれば、どうしても“様子を見ましょう”という対応にならざるを得ず、そのままお帰りいただくしかありませんでした。しかし、交番へ相談に来る方には“何かしてもらえる”という明確な期待がある。期待されても答えることができない。動いても感謝されにくい。そのような構造のなかで、“そもそも被害者をつくらない社会にするにはどうすればいいか”という問いが自分の中に芽生えました。
「被害者をつくらない社会」を目指すなら、そもそも「事件未満」の段階からアプローチし、困っている方に寄り添う仕組みの必要性を実感したことが起業のきっかけです。キャリア官僚として防犯政策に携わる道も模索しましたが、最終的に、民間から社会を変える挑戦へと舵を切りました。
―この事業を民間でやることの意義とは何でしょうか?
行政のサービスにおいては、実害や権利の侵害のように、法的な判断基準をもとに制度が設計されています。私たちが今取り組んでいるのは、そこに至る手前の“感情のぶつかり合い”の領域であり、行政や既存の仕組みでは対応しきれない“グレーゾーン”です。感情のもつれをどう評価して、どう収めていくかというのは、法整備だけでは割り切れない部分が多いですよね。スピーディかつフレキシブルに対応できるのは民間だからこそ、だと考えています。

―ヴァンガードスミスのコーポレートサイトを開くと、「困っている人を助ける」というシンプルながらも力強いメッセージが目に飛び込んできます。「困っている人を助ける」という価値観は、現在どのように事業、組織に反映されていますか?
「困っている人を助ける」は、6年ほど前ホームページをリニューアルするときに、私たちの行動と価値観を最も表している言葉として、改めて選びました。
私の警察官時代の元上司・現取締役の大川原さんの「困っている人がいるのであれば、今すぐ行ってあげようよ」という口癖が起点であり、サービス設計時から繰り返し使われていた重要な言葉です。
当社は社員全員が「困っている人を助けたい」という想いに共感して入社しています。現在も特別に意識づけをしなくてもこの理念は自然と根付き、日々の業務の中でその価値観を体現してくれています。
解決の現場で磨かれたサービスと支援ノウハウ
現場対応で蓄積されたのは、トラブル時における心理・地域性への理解・警察官時代に培われた法令に関する知識などを統合的に扱う支援力。 2025年には解決支援策の一つとして〈身辺警護(4号警備)〉が追加提供され、サービスは新たな領域へと拡張されている。すべての根底にあるのは「社会全体に安心と安全を届けたい」という使命感だ。
―初期の支援事例や印象に残っている案件を教えてください
初期は私1人で現場対応していましたが、支援事例として印象に残っている2つの案件があります。
1つ目は、DV被害の後遺症に苦しむ女性の支援です。家中の隙間を埋めないと眠れないほど不安を抱えており、ゴミ屋敷のような状態でした。自治体や医療機関の支援も受けられていなかったため、治療につなげるサポートを行いました。
2つ目は、近隣住民から威嚇されて不安と恐怖心を抱えていた母子家庭の支援です。相手男性の背景調査と家族への働きかけを通じて相手男性が退去することになり、問題を解消しました。
いずれのケースも、現場でのコミュニケーションによって早期に解決の糸口が見え、「このサービスには確かな意義がある」と実感する原点となりました。

―他に類似サービスがなかったことから、サービス開始当初はなかなか相談が来なかったとのことですが、そのような時期をどう乗り越え、どのようにして認知・信頼が広がっていったのでしょうか?
「できます!」と言っても信用されにくい分野なので、最初は不動産会社経由で紹介された案件一つひとつに寄り添う姿勢を持ちながら誠実に向き合い、地道に実績を積み重ねることで信頼を築いていきました。信頼を得るまでに4年間を要しましたが、必要な期間だったと思います。
一方で、経営者の方たちには「単なる支援ではなく、日本の防犯の仕組みそのものを変えるための取り組みであり、社会改善が目的だ」と熱意を持って語ることで強い共感を得ました。「困っている人を助けたい」という姿勢に加え、“なぜやるのか”について言葉を選びながら丁寧に伝えたことが、信頼と認知の拡大につながったと思っています。
―10年間で蓄積されたノウハウ、ヴァンガードスミスだからできる強み<唯一無二である理由>を教えてください。
「近隣トラブルは解決できない」とされていた10年前から、この領域でやり続けてきたこと自体が大きな価値だと思っています。従来、近隣トラブルは警察に相談する以外の方法がありませんでした。これは、トラブルを実害ベースで捉えていたためです。
当社は心理学や近隣トラブルの研究者の知見を取り入れ、「当事者の感情を起点にトラブルを捉え、沈静化を図る」という独自のアプローチを確立しました。これを仕組み化することで10万件を超えるトラブルを解決に導いてきました。それを実行する経験豊富かつ冷静に対処できる元警察官の人材が、当社の唯一無二の強みです。
相談員が全員元警察官で構成されていることも当社の大きな価値のひとつです。元警察官でなければできない仕事ではないものの、近隣トラブルの解決という職種上、冷静な傾聴力、公平な対応力が不可欠です。また、「感謝されたい」という想いや価値観、正義感を持っていないと継続できない業務でもあるので、自分と同じ経験・想いを持つ元警察官にこだわって採用しています。

―顧客や社会全体に、どのような影響・価値を届けたいと考えていますか?
従来の行政サービスは「被害が起きた後の対応」が中心でしたが、当社の事業は「被害を未然に防ぐこと」に価値を置いています。早期に相談し、適切に対処すればトラブルや犯罪は防げるという価値観を社会に広めたいと考えています。これは健康に例えるなら「病気になってから治す」ではなく、「ならないように予防する」発想ですね。
防げるという意識の定着=防犯インフラの構築と考えており、社会全体にこの価値観を根付かせることが目標です。
ヴァンガードスミスの本質――組織文化と信頼のかたち
10年間で変化した部分と、守り抜いてきた信念。 現場と組織が一体となって支援を届けてきたからこそ育まれた「ヴァンガードスミスらしさ」とは何か。ともに働く社員やパートナー企業との関係性も、ヴァンガードスミスの魅力を語る上で欠かせない。
ー創業から10年で、最も変わったこと・変わらなかったことについて教えてください。
10年前は「近隣トラブルが解決できるわけない」と思われていました。しかし、今では「ヴァンガードスミスなら解決できる」と信頼・評価される存在になり、社会全体が「近隣トラブルは解決できるかもしれない」と認識を変え始めていることが最大の変化だと感じます。
一方で、組織が大きくなり、相談対応の質も向上した一方で、「寄り添い切る」という価値観は創業当初から変わらず継承されています。また、勤勉さ・おせっかいさや寄り添いきれる胆力と価値観への共感が社内全体に根付いていることも変わっていません。これは、変わらず組織として大切にしてきた文化や価値観だといえます。
―近隣トラブル解決支援サービスの国内普及率50%を目標として掲げています。その実現のために、一緒に働くメンバーやパートナー企業に対して、どのような存在でありたいですか?
人から感謝されて生きることの価値を感じられることは、当社ならではです。メンバーとは、その価値を体現できる場を一緒に作っていきたいですね。
パートナー企業に対しては、困ったときに最初に相談される存在でありたいと思っています。店舗防犯など新たなサービスもそうですが、いざというときに頼れる存在として認知されたいと考えています。
次回予告 ――現場発想で生まれた〈店舗防犯サービス〉へ
次回は、〈近隣トラブル解決支援〉の知見を応用して開発された〈店舗防犯サービス〉について。 「被害者をつくらない」という思想のもと、現場発想で設計された次世代型の防犯のあり方を探ります。
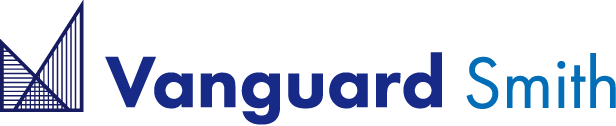
 前の記事へ
前の記事へ