Blog
- 【ヴァンガードスミス10周年記念企画④価値観】 「“人を助ける柔道”から生まれた発想――全国の道場を、防犯の拠点に」

柔道の本質的な価値は、勝敗を競うことだけに限定せず「人を守るための心」」を育むことにあります。 ヴァンガードスミスの創業者・田中が柔道を通じて学んできた精神は、近隣トラブル解決支援という現場でも、防犯の組織運営においても、大きな影響を与えてきました。
本記事では、田中が警察官時代から培ってきた価値観をたどりながら、なぜ今「全国の道場を防犯の拠点に」という構想に至ったのか。その背景と想いに迫ります。
柔道が教えてくれた、“守るための強さ”
ー改めて、柔道との出会いや、現在も続けている理由を教えてください。
私が柔道を始めたのは、警察官になった22歳のときです。警察学校で柔道コースを選び、柔道によって現場で必要な力を磨きました。退職後も道場に通い続け、柔道は人生の一部となっています。現在は会社の柔道部でも稽古を重ね、身辺警護に欠かせない体制づくりに役立てています。
柔道を続ける意味を強く実感したのは、北海道から関東へ移り住んだときでした。柔道着を持って地元の道場に足を運ぶと、すぐに柔道仲間として受け入れてもらえたのです。土地勘も知り合いもない中で孤立せずにいられたのは、柔道という共通言語を介したコミュニティのおかげでした。柔道が持つ「人をつなぎ、支える力」を身をもって体験し、その経験が今も私を道場に向かわせています。
私たちの事業では、柔道家の力を地域防犯に活かす構想を進めており、その取り組みが、柔道の総本山とも言われる講道館とのご縁につながりました。私自身も講道館で稽古に臨みつつ、以前から通っている道場でも柔道を続けています。

ー柔道の教えで、今も強く心に残っている言葉や精神はありますか?
やはり「自他共栄」です。柔道家、嘉納治五郎先生の言葉として、多くの方が柔道を通じて触れてきた精神だと思います。相手も自分も尊重し、ともに栄えていくという考え方であり、私はこの言葉をとても大切にしています。「自他共栄」という考え方は、当社のサービスにも深く息づいています。
ー事業の根幹にある「自他共栄」の考え方は、サービスや組織運営にどのように影響していますか?
「自他共栄」とは、互いに助け合い、励まし合い、高め合うことです。自分も相手も共に栄えるようにという配慮の精神にも通じ、これは私たちが取り組む近隣トラブルの解決支援に非常に近い考え方だと思います。
現場で大切なのは相手を否定するのではなく尊重する姿勢。誰もがこの考え方を持つことができれば、無用な争いは減り、地域のトラブルも少なくなっていくと信じています。
なお、「自他共栄」は最初から掲げていた理念ではなく、事業を続ける中で自然と体現し、たどり着いた「実現したい世界観」として確立されました。
日々の業務にこの精神を取り入れることで、組織は自然と実践力を備え、より強いチームへと成長してきました。当社では、入社後に柔道を始める社員もいれば、柔道経験がなくても相談業務を通じて「自他共栄」を体得していく社員もいます。困っている人を見つければ自然に声をかけ助け合う文化が根づいており、組織としても「共に栄える」意識で、メンバー同士の信頼関係を大切にしています。

“守り抜く力”を社会へ――柔道とつながる身辺警護サービス
ー2025年1月から、近隣トラブル解決策の一つとして「身辺警護(4号警備)」が追加提供開始されました。サービス概要や拡張の背景について教えてください。
会員制サービスの中で、会員様が「身の危険を感じる」と明白に感じられる場合、従来の行政サービスだけでは常時対応できない場面があります。そこで私たちは元警察官で構成する専門部隊による身辺警護を、新たに付帯サービスとして提供することを決めました。追加料金は不要で、従来のサービスにそのまま組み込まれています。
きっかけは採用面接の中で「もっと身近に身辺警護を提供する仕組みが作れないか」という退職を決めていた現職警察官からの相談でした。身辺警護は一定の身体的リスクを伴うため、慎重に検討しましたが、社会に“本当に危ないときに守ってくれる仕組み”が存在しない現状に対し、必要性を強く感じました。
防犯支援を突き詰めた結果、危機時に実動で守る実行部隊の重要性が明確になりました。DVやストーカー、不動産業務におけるトラブル対応時のリスクなど、身体的危険が想定される場面では、法令に基づく4号警備として寄り添う対応を行っています。将来的には、警察との連携による体制構築も視野に入れていきたいと考えています。
背景には、「危険を感じている方を誰かが守らなければならない」という現場での実感がありました。私たちがその役割を担うことで、会員様により大きな安心を届けたい――その思いから、身辺警護の追加提供に至りました。
ーこの付帯サービスは、社会全体にどのような価値や影響をもたらすと考えていますか?
非常に大きな価値があると考えています。防犯を突き詰めていくと、最後に「本当に危ないときに守り抜く実動部隊」が必要だという結論に行き着きます。これまでは親族に頼るしかないようなケースもありましたが、私たちの体制があれば、そこをカバーできるのではないかと思っています。これは防犯インフラとして大きな変化になると感じています。
追加提供直後から提携企業様からは「そこまでやるのか」「従業員や入居者も含めて、本当に危ないときに守ってくれるということはすごいことだね」と驚きと評価の声をいただきました。
さらに「そんな事業に参画したい」と新たに入社を希望する人材も現れるなど、今後こうした発信を重ねることで、仲間も増え、警察官経験者の新たな活躍の場にもつながっていくと期待しています。

ー身辺警護サービスにも、柔道は生かされているのでしょうか?
身辺警備サービスの基盤には、日々の鍛錬があります。現在当社には20名の身辺警護員登録者が在籍し、柔道や逮捕術のトレーニングを継続的に行っています。
レクチャーは元警察官のメンバーや師範クラスの術科が担当し、内部で体系的に運営されているのが特徴です。柔道を続けることは単なる自己鍛錬にとどまらず、サービスの拡張や質の向上にもつながっています。
「道場を防犯の拠点に」という構想
ー「柔道×防犯」という発想は、どのように生まれたのでしょうか?
柔道は1882年に講道館で誕生し、ほどなく警察にも取り入れられ、日本中に広がっていきました。警察そのものが防犯の組織であることを考えると、柔道と防犯はもともと非常に密接な関係にあると感じています。
柔道には、心身の鍛錬や人格形成を重んじるという武道としての精神があり、それは防犯に欠かせない「冷静さ」や「自制心」を育みます。防犯=力の強さと思われがちですが、本質は冷静に判断し、衝動を抑える力にあります。そうした柔道の精神とインフラを活かし、私たちの防犯活動を広げ、防犯の新しい拠点をつくっていきたいと考えました。
ー全国の柔道場を“防犯の拠点”にする構想とは、どのような取り組みですか?
防犯を地域に根づかせるためには、地域ごとに「監視」「相談」「情報発信」といった機能が必要です。柔道場は全国にあり、すでに子どもたちが集う地域の拠点となっています。そのインフラを活用し、防犯に関する情報発信や相談対応を行い、子どもたちへの防犯教育を進める。そうした活動を通じて、地域の安心と安全を広げていく取り組みです。
実際に、現在は広島・埼玉・北海道などで、柔道家の先生方が現地訪問を始めています。私たちの発信を見た道場の方が、「一緒に取り組みたい」と声をかけてくださったことがきっかけです。
具体的には、柔道場を運営する先生方が防犯の考え方を地域に発信したり、道場に通う子どもたちに伝えたりする取り組みです。相談窓口の機能を道場に設けたり、私たちの訪問業務の一部を柔道家に担っていただいたりと、既に実践的な仕組みも動き始めています。
今後は、柔道指導者や保護者、自治体とも連携しながら、道場を「地域の防犯拠点」として全国に広げていきたいと考えています。
ー「柔道×防犯」という価値観が、これからの社会にどう貢献できると思いますか?
柔道を単なる競技としてではなく、人間形成の場として広げていきたいと考えています。私は、柔道を通じて育まれる強さや人としての在り方は、地域社会の安全や安心につながるはずだと信じています。
こうした価値を防犯と結びつけて発信することで、日本ならではの防犯システムを形にできれば、その仕組みはやがて世界の困っている人々をも支える力になるのではないでしょうか。
▶本記事のインタビュー動画はこちら
次回予告「“防犯のインフラ企業”へ――次の10年、さらに全国に広げる安心と安全」
創業から10年、近隣トラブル解決を軸に独自の防犯支援を築いてきたヴァンガードスミス。
次回はいよいよ最終回。品質管理体制の強化、人材育成、防犯ネットワークの全国展開など、これからの10年で描く「防犯のインフラ企業」としての未来像に迫ります。
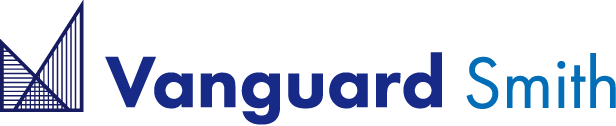

 前の記事へ
前の記事へ